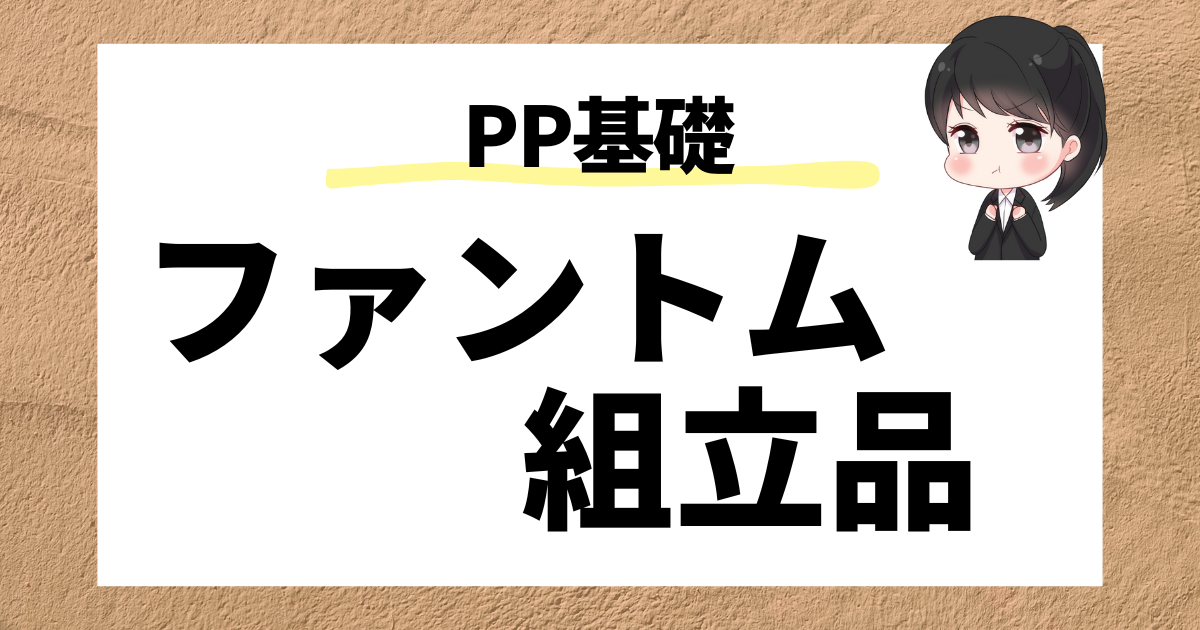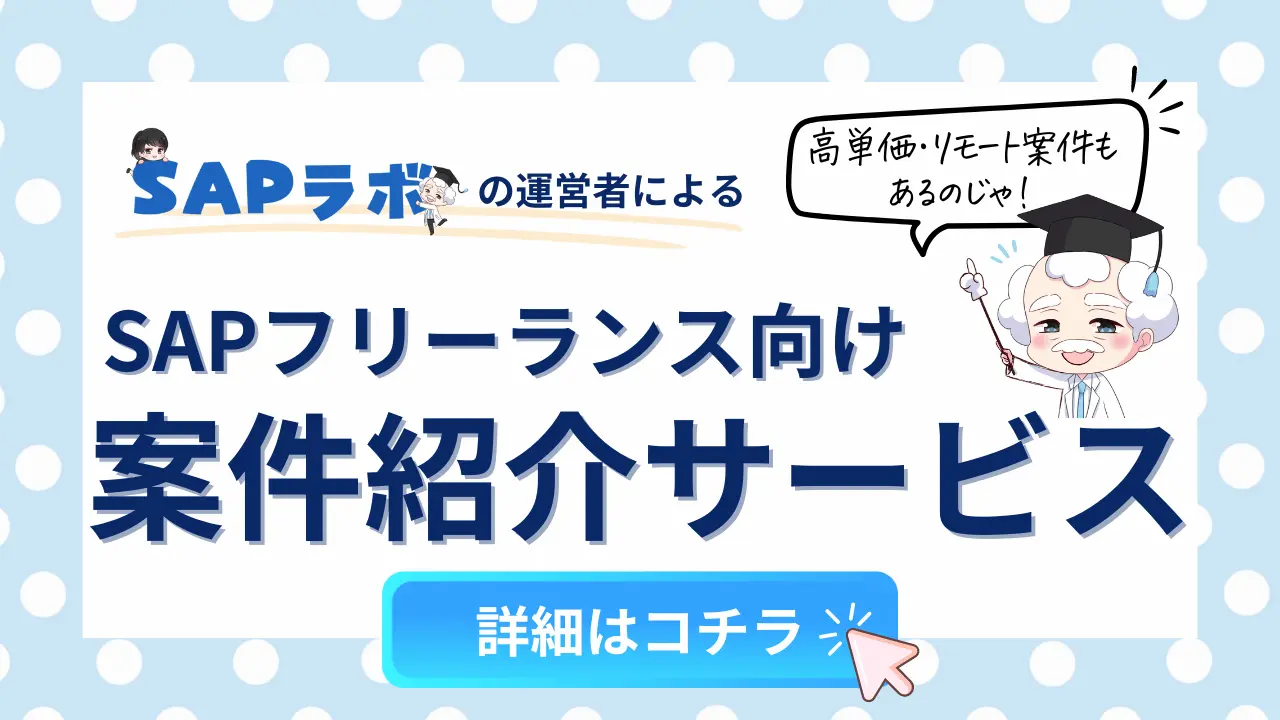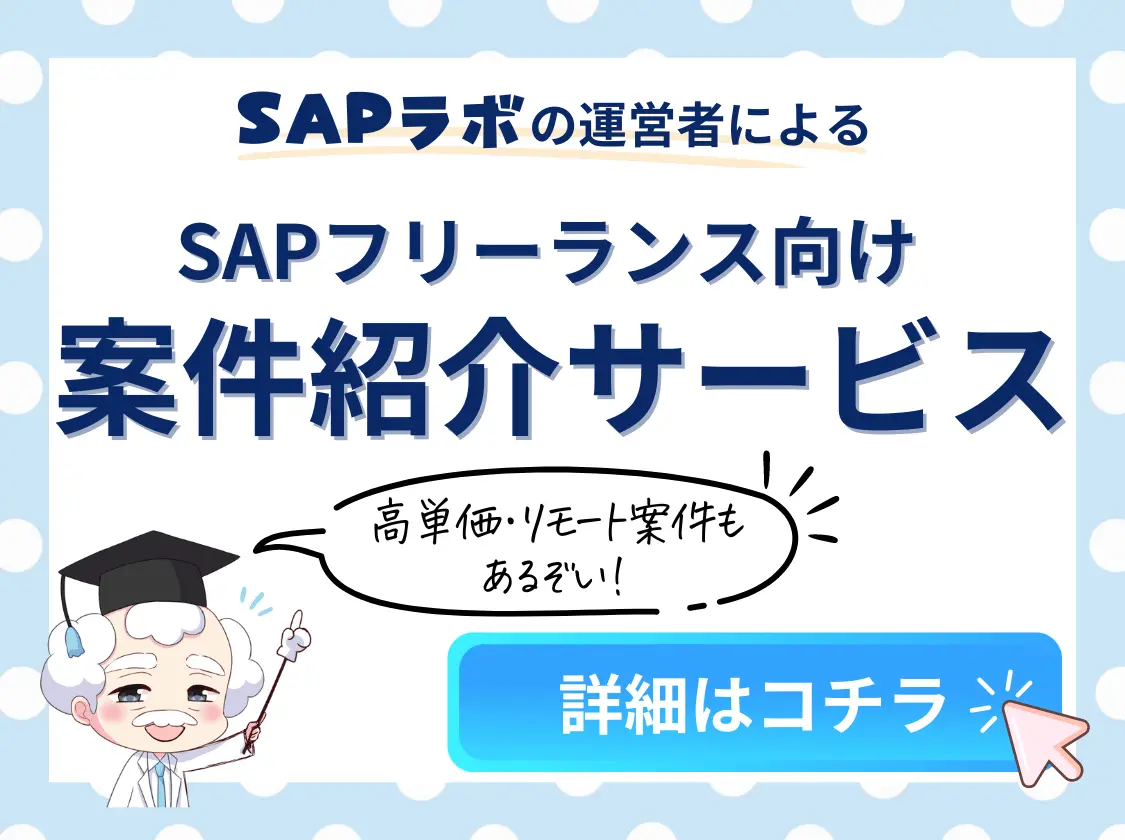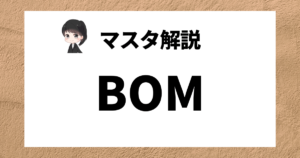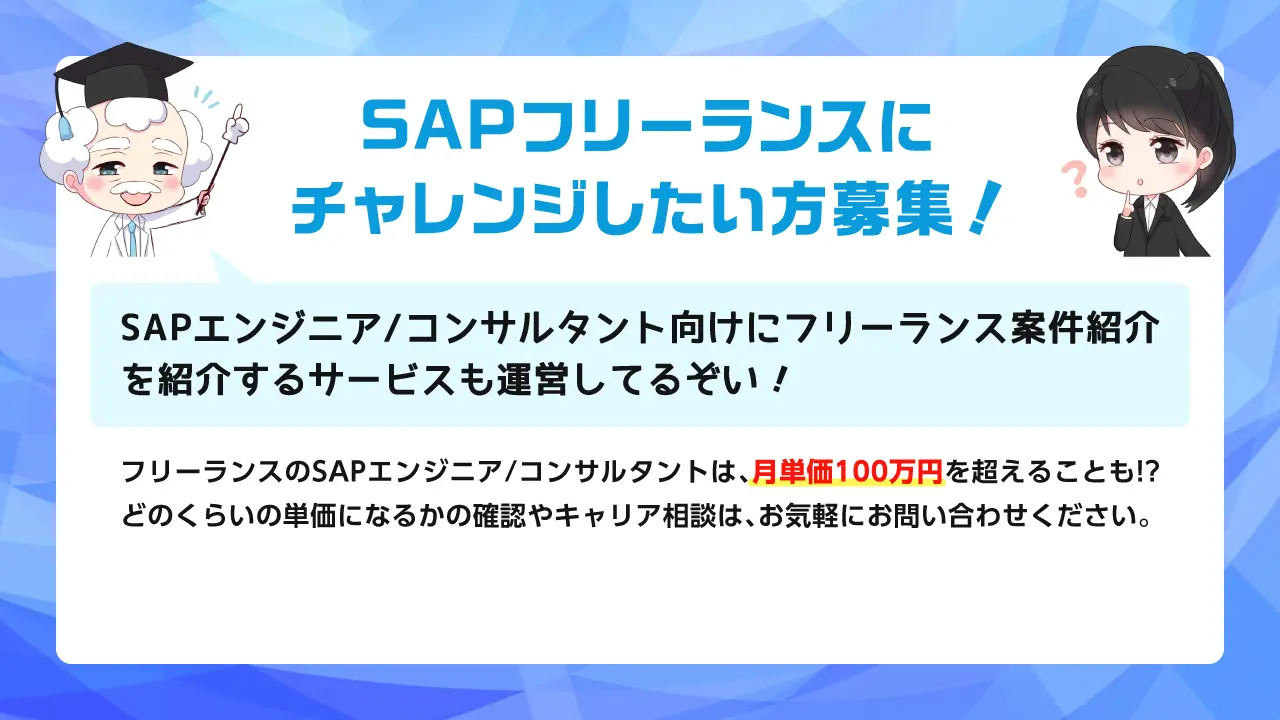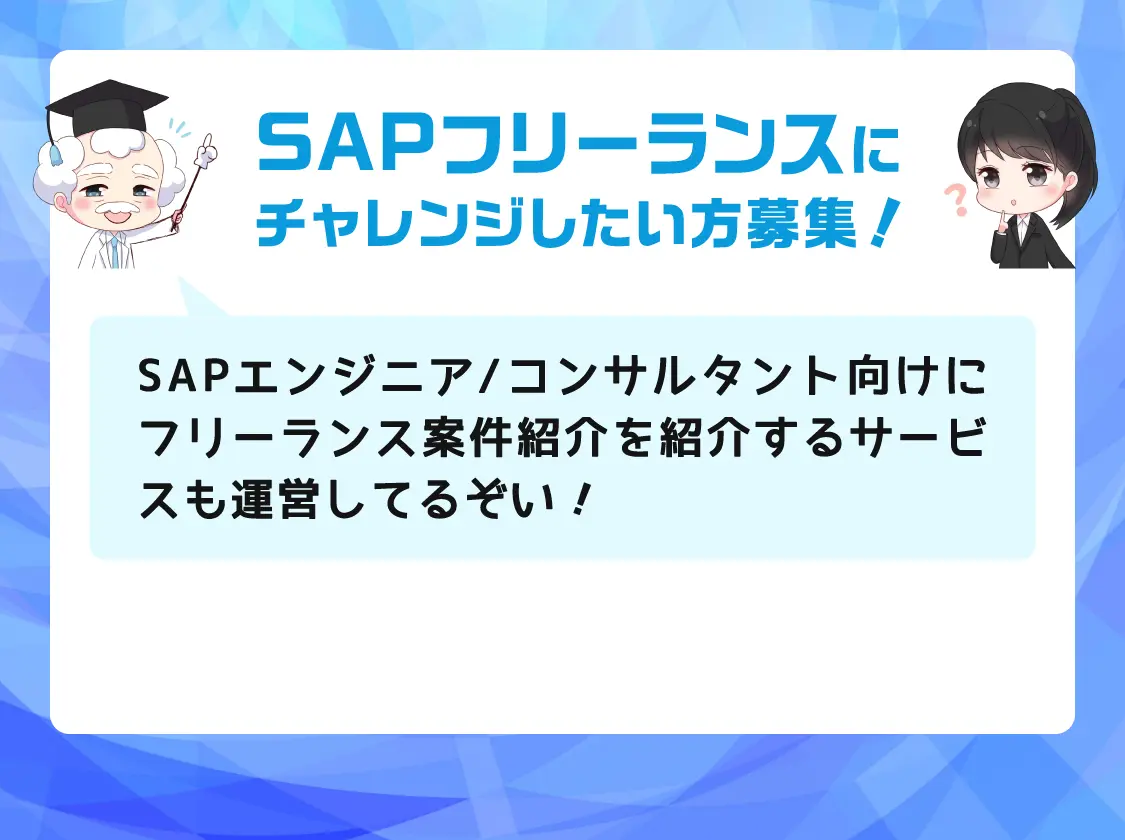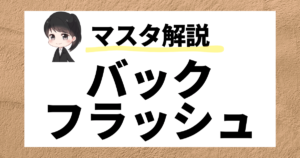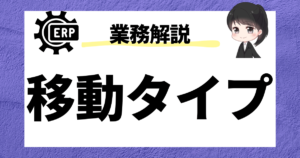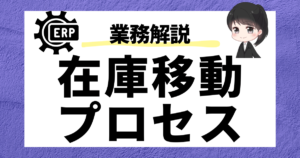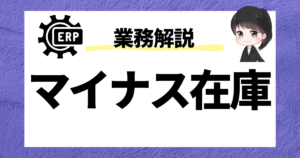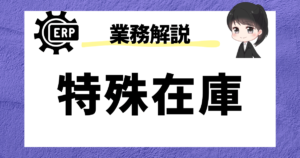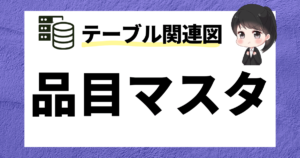この記事を読むメリット
- ファントム組立品の役割と設定の本質を理解できる
- BOM内の構造展開、MRPの対象可否、品目マスタ上の注意点をわかりやすく整理します。
- MRPタイプ・原価計算などのシステム挙動を、具体例で把握できる
- 調達タイプXや各種MRP設定における動作パターンを理解することで、設計・検証がスムーズになります。
直訳すると、「幻、お化け、見せかけの」という意味じゃ
SAPにおける生産計画や製造指図に関わるプロセスの中で、「ファントム組立品(Phantom Assembly)」という概念は意外と見落とされがちですが、BOM構造の設計において非常に重要な役割を果たします。
本記事では、ファントム組立品の概要、設定方法、使用シナリオ、および実務上の注意点について、技術的な視点からわかりやすく解説します。
この記事のポイント
ファントム組立品とは
ファントム組立品とは、物理的に在庫として管理されることはなく、BOM上の中間階層としてのみ使用される仮想的な部品構成のことです。製造工程では実際に製造・仕入れされるわけではなく、その構成をそのまま親品目のBOMに展開することで、製造プロセスを簡略化する役割を担います。

利用シーンとメリット
よくある利用シーンとしては、共通構成部品の簡略管理で使用されます。
複数の最終製品に共通する部品群をまとめて管理することで、メンテナンス性を向上させることができます。例えば、下記の画像の様に、共通部品群をファントム構成品を使用し割り当てることで、その共通部品群に変更があった際に、ファントム構成品1つを修正すれば、すべてにその変更内容を反映させることができます。
また、特定の工程ごとに使用する部品をひとまとめにし、工程設計を整理しやすくすることもできます。
ただし、実在品との区別がつきにくいとかえって不便になりかねませんので、品目テキストなどで区別しやすいような工夫をすることがポイントです。

ファントム組立品の設定方法
ファントム組立品の設定は、大きく下記の2通りの方法があります。
- 品目マスタで設定する
- T-CODE: MM01 / 02(登録 / 変更)を使用し、品目マスタのMRP2タブから項目:特殊調達「50:ファントム組立品」を設定します。
- BOMマスタで設定する
- T-CODE: CS01 / 02(登録 / 変更)を使用し、BOMマスタの構成品目の明細画面から特殊調達「50:ファントム組立品」を設定します。
 ファントム組立品の登録方法1
ファントム組立品の登録方法1
 ファントム組立品の登録方法2
ファントム組立品の登録方法2
一般的には、品目マスタで設定することが多いですが、「同じ品目を通常品目とファントム組立品の両方で使用する」といった場合に設定場所を使い分ける必要があります。
例えば、いつもは通常品目として利用するが、特定のBOMではファントム組立品として使用する場合、品目マスタでは特殊調達を空欄にしておきます。そして、特定のBOMマスタにおいて、特殊調達「50:ファントム組立品」を設定します。
逆に、品目マスタ上で特殊調達「50:ファントム組立品」を設定し、特定のBOMマスタにおいて、展開タイプ「02:ファントム組立品オフ」を設定することで、そのBOMにおいては、ファントム組立品の性質を無効化することができます。
もっと詳しく💡
この特殊調達タイプという項目の設定値を定義しているカスタマイズを紹介します。
SPROのIMG照会パスは下記の通りです。(T-CODE: S_ALR_87006492 )
在庫/購買管理 > 消費主導型計画 > マスタデータ > 定義: 特殊調達タイプ
ここで下記画像のように、ファントム組立品を定義しています。その為、コードの番号はこのカスタマイズの設定に依存しています。
 特殊調達タイプのカスタマイズ
特殊調達タイプのカスタマイズ
ファントム組立品以外にも、受託品や外注なども同様に定義されているぞい!
ファントム組立品の取扱い
ここまで、品目マスタからファントム組立品を登録する手順を解説してきましたが、実際にその品目を使ってBOMマスタを登録したり、原価計算を回したりした際には、どのような挙動をするのでしょうか?
1.BOMマスタの登録
上位品目(親品目)としても、構成品目(子品目)としても、基本的に通常の品目と同じように設定することが可能です。オペレーションも特に変わりません。
ちなみに、構成品目としてファントム組立品を登録する際に、明細カテゴリを“L:在庫品目”と設定してもファントム組立品の設定をしている限り、在庫品目として扱われることはありません。
また、下記の画像のように、ファントム組立品の場合、ファントム組立品という項目にチェックが入っており、ファントム組立品であることが一目でわかるようになっています。
 BOM登録の登録画面
BOM登録の登録画面
もちろん、BOM展開レポート(T-CODE:CS11、CS12)を使用した際は、下記の様にファントム組立品も構成品の1つとして表示されています。
 SAP BOM展開(CS11)
SAP BOM展開(CS11)
2.原価計算
ファントム組立品は、製造や在庫を伴わず、あくまで「BOM(部品表)上の論理的なまとめ役」として機能します。そのため、原則としてファントム組立品自体には原価が発生しません。
原価計算(例:標準原価計算)では、ファントム組立品をスキップして下位の構成品(子部品)の原価を上位品目に直接集計する仕組みが取られています。T-CODE:CK11N(積上げ原価計算)で原価を展開する際も、ファントム組立品は中間ノードとして無視され、構成品目の原価がダイレクトに親品目に集約されます。
下記の画像は、上記のBOMマスタで登録した完成品FG2-CPの原価計算を行った時の結果です。
赤枠の原価計算構成の中に、ファントム組立品として登録した品目“SG4-CP”がないことが分かります。
 原価計算(CK11N)
原価計算(CK11N)
3.MRP
ファントム組立品は、MRP実行(T-CODE: MD01/MD02など)において特殊な扱いをされます。
具体的には、ファントム組立品自体の所要量は計算されず、下位の構成品のみが上位品目の所要量に応じて通常通り計算されます。MRPの実行結果は、構成品目のMRPタイプにより異なります。
ファントム組立品はあくまで、在庫や仕掛品としては管理されず、あくまで概念的なものですので、所要量計画や発注は行われません。
しかし、余談ですが、品目マスタ上でファントム組立品にもMRPタイプは登録可能です。これはあくまで「形式的に入力可能」というだけで、実際のMRP実行では意味を持ちません。
さらに、バックフラッシュ時には、ファントム組立品の構成品目に対する在庫移動のみが転記されます。ファントム組立品は、バックフラッシュ済みとしてマークされますが、在庫移動をトリガすることはありません。
まとめ
SAPにおけるファントム組立品は、製造業におけるBOM管理の柔軟性と効率性を高める重要な仕組みです。物理的に存在しないが、論理的な構成を保持することで、部品管理・工程設計・生産計画において合理化を図ることができます。
ただし、設定を誤ると実在品と混同されるリスクもあるため、「特殊調達キー=50」 の設定と、BOM展開時の挙動を十分に理解したうえで運用することが肝要です。
実務でのBOMメンテナンスやMRP設定時に、「この部品、本当にファントムで良いのか?」という視点を忘れずに活用していきましょう。
ファントム組立品の解説は以上じゃ~!
BOMマスタについては、下記記事が参考になるぞい!
あわせて読みたい
【SAP PP】BOM(Bill of Materials)について解説
この記事を読むメリット PPモジュールのBOMマスタについて基本を理解することができます。 今回はSAPにおけるBOMマスタ(Bill of Materials)について解説していきます。B…