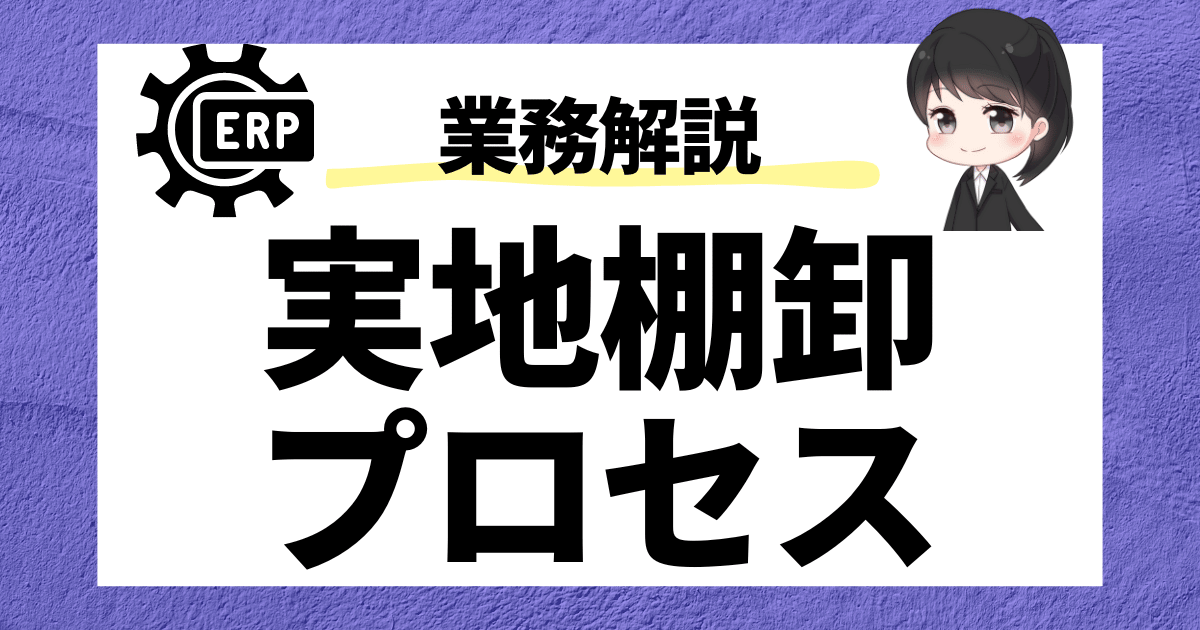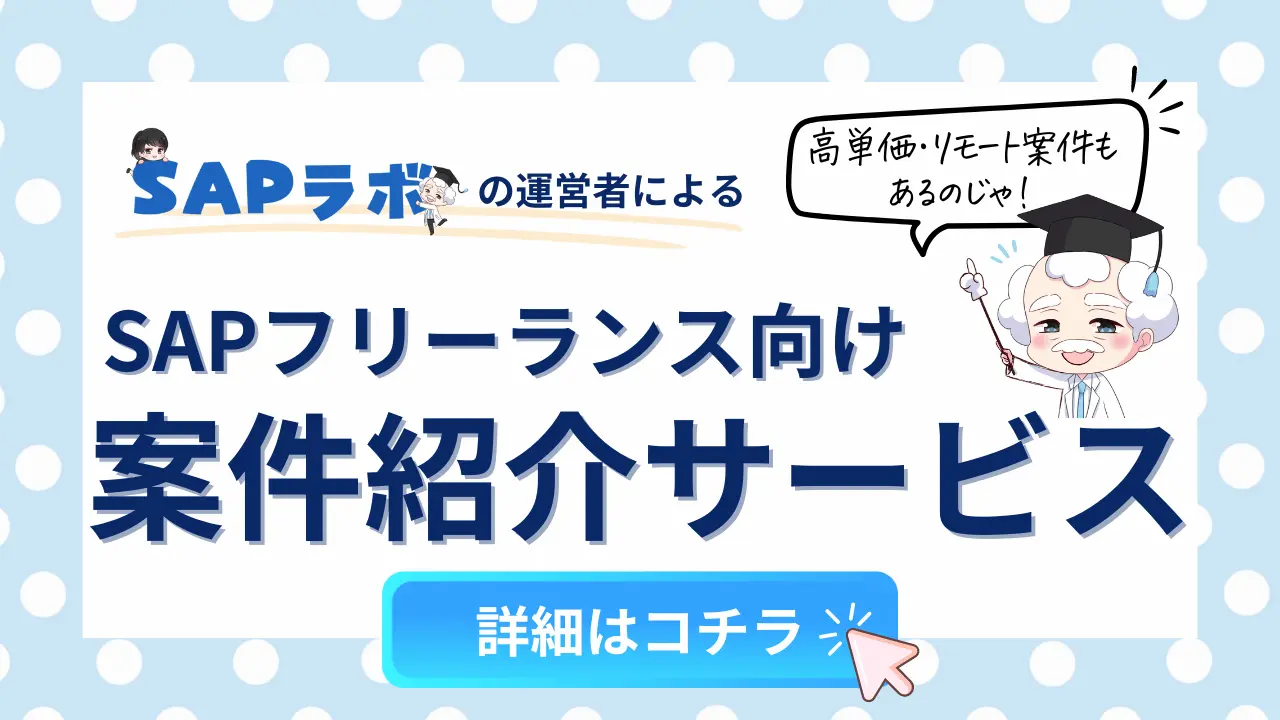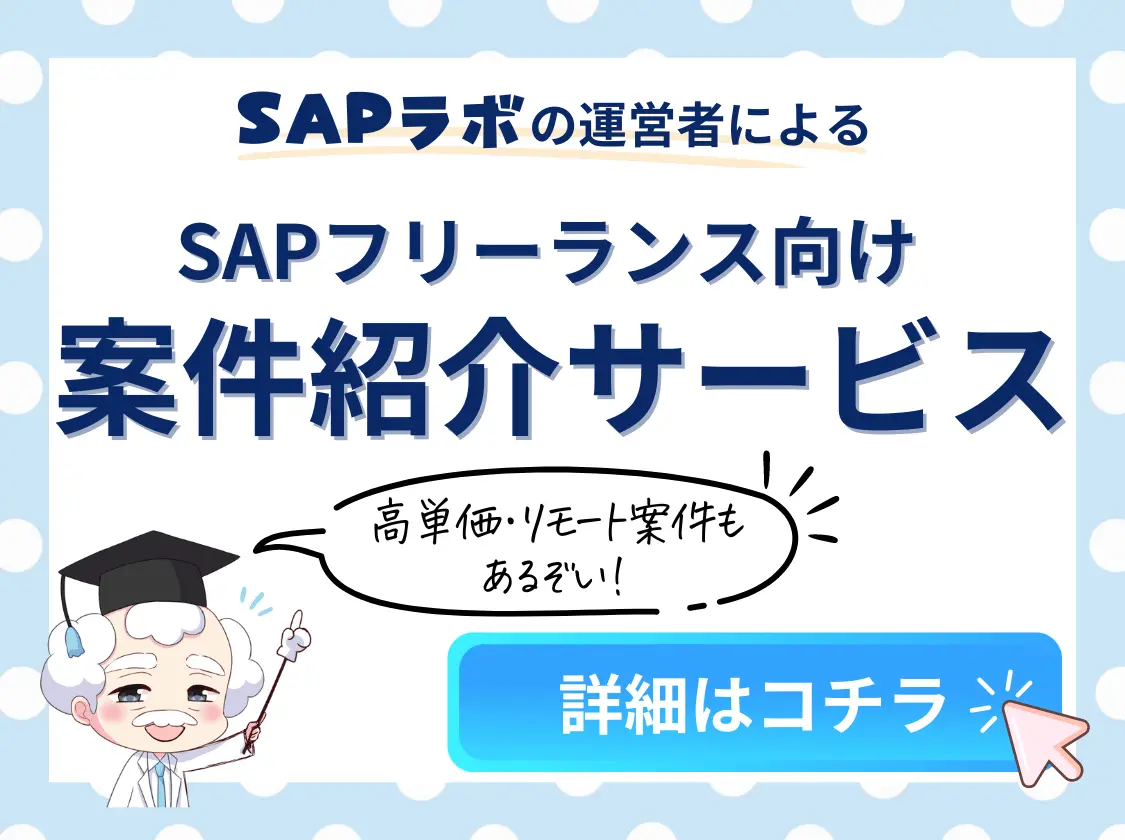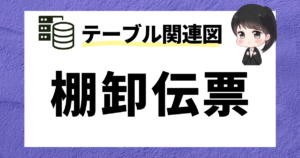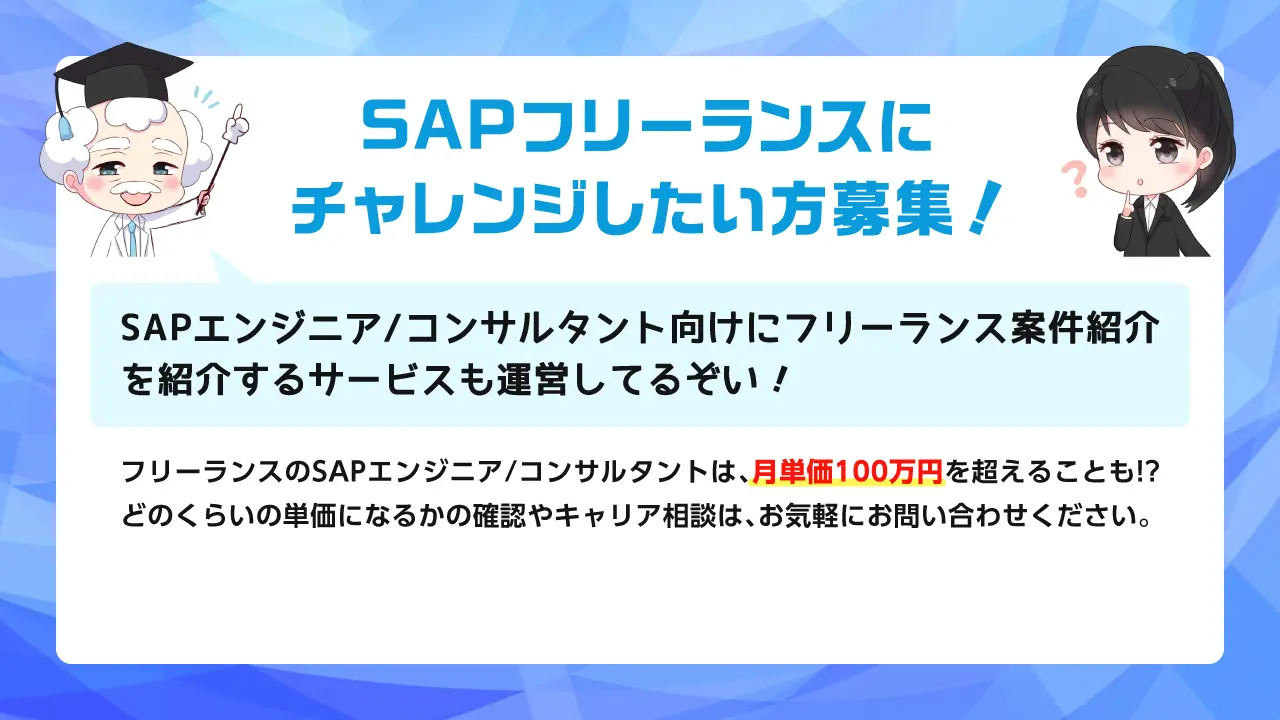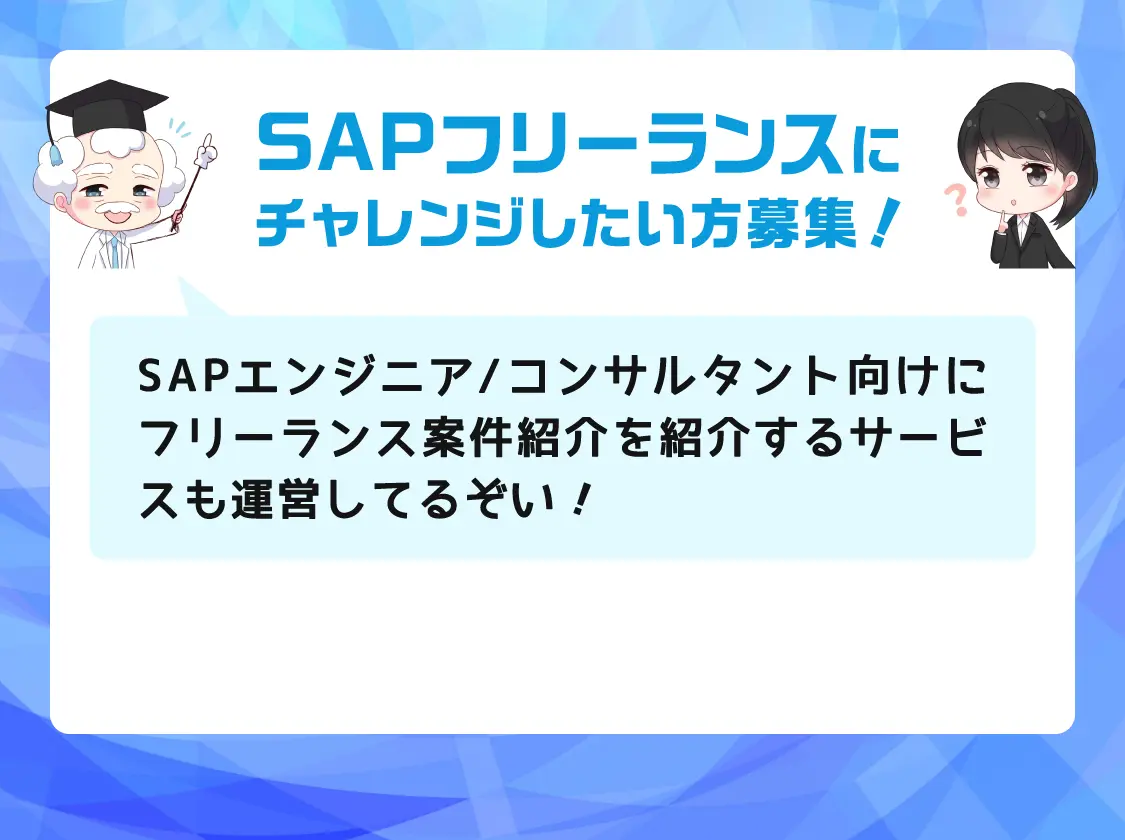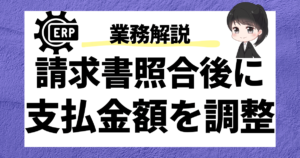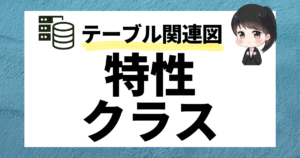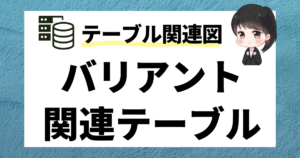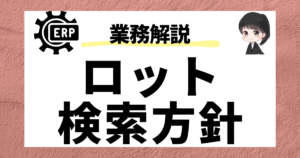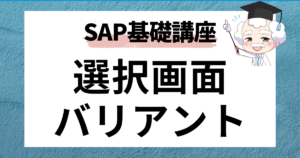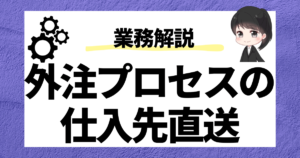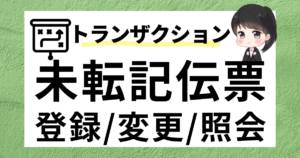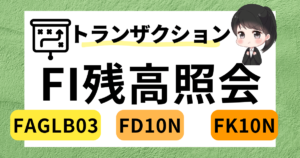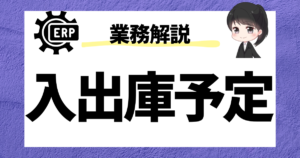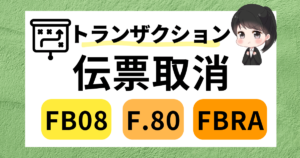この記事を読むメリット
- SAPを用いた実地棚卸業務プロセスと、使われるトランザクションコードについて理解できます。
SAPを用いた棚卸業務はどうやって行われているんだろう…?
在庫を抱える会社では、定期的に在庫の棚卸業務が行われるのが一般的です。
SAPで在庫管理をしているような中~大規模な企業では実地棚卸業務は必須の業務プロセスになっているでしょう。
今回はSAPを用いた実地棚卸プロセスについて、具体的なトランザクションコードもふまえて解説していきます!
この記事のポイント
実地棚卸とは?
実地棚卸とは、企業や組織が実際に保有している在庫を物理的に確認し、その数量を記録する作業を指します。
SAPでは、SAPで管理されている在庫数量と実際に保管されている在庫数量に差異が無いか確認します。
もしSAPで管理されている在庫数量と実際に保管されている在庫数量に差異がある場合は、実際に保管されている在庫数量に合わせてSAPの在庫数量を変更し、それに伴う会計伝票を登録させる必要があります。
T-CODE:MIGOにて入出庫伝票を直接登録する方法もありますが、棚卸業務のログを残しておくために棚卸伝票を用いる方法が一般的かと思います。(もちろん運用上、棚卸伝票が不要な場合もありえます)
SAPを用いた実地棚卸プロセスを、具体的なトランザクションコードをふまえて確認していきましょう!
実地棚卸関連の基本のプロセス

SAPでの実地棚卸では、一般的に以下のプロセスが行われます。
- 棚卸伝票の作成
どのプラント・保管場所について、どの品目の棚卸をするかが定義されている棚卸伝票を作成します。
■T-CODE:MI01では手動で棚卸する品目を入力する必要があります。
■T-CODE:MI31ではプラントや保管場所等の条件でまとめて一括で棚卸伝票を作成することが可能です。
- 実際の在庫数量を入力
棚卸伝票に対して実際に保管されている在庫数量を入力します。
■T-CODE:MI04にて在庫数量を入力します。T-CODE:MI24(棚卸伝票一覧)やT-CODE:MI20(棚卸差異一覧)から在庫数量入力画面へ遷移することも可能です。
■T-CODE:MI05にて、T-CODE:MI04で入力した在庫数量を変更することができます。
- 在庫差異を転記
棚卸伝票に対して、SAPで管理されている在庫数量と実際の在庫数量がある場合に、実際の在庫数量に合わせるため在庫差異を決済処理します。それにより、入出庫伝票と会計伝票が転記されSAPで管理されている在庫数量が実際の在庫数量に変わります。
■T-CODE:MI07では棚卸伝票を個別に決済処理を行います。T-CODE:MI24(棚卸伝票一覧)やT-CODE:MI20(棚卸差異一覧)から決済処理画面へ遷移することも可能です。
■T-CODE:MI37では複数の棚卸伝票をまとめて決済処理することができますです。
実際に担当者が数えて紙で記録していくために棚卸伝票を印刷することもあります。
その際はT-CODE:MI21Nで棚卸伝票を印刷することも可能です。
また、SAPでの棚卸業務では派生したパターンもあります。以下はパターンの一例です。
- 最初に棚卸伝票を作成せず、T-CODE:MI09で実際の在庫数量を入力することでシステム在庫数量と実際の在庫数量の情報を持った棚卸伝票伝票を作成することが可能です。決済については前述通りです。

- 棚卸伝票を作成した後にT-CODE:MI08にて実際の在庫数量を入力することで決済処理まで一気に行うことも可能です。

棚卸伝票の作成
棚卸伝票を作成するときにはいくつか作成パターンがあります。
T-CODE:MI01では手動で棚卸する品目を入力する必要があります。
一方でT-CODE:MI31ではプラントや保管場所等の条件を指定し、まとめて一括で棚卸伝票を作成することが可能です。
T-CODE:MI01で1品目ずつ棚卸品目を入力するのは大変なので、一般的にはT-CODE:MI31でまとめて棚卸伝票を作成することが一般的です。
また、棚卸伝票の重要な設定として「転記ブロック」と「棚卸在庫凍結」というものがあります。これらは棚卸伝票のヘッダで管理されています。
転記ブロックについて

転記ブロックフラグにチェックをすることで棚卸が完了するまで、そのプラント・保管場所に保管されている品目について入出庫伝票を登録できなくすることが可能です。
棚卸業務が完了すれば転記ブロックが解除され、入出庫伝票を登録することができるようになります。
帳簿在庫凍結について

帳簿在庫凍結フラグにチェックをすることで、棚卸伝票を登録した時点の在庫数量をSAP上の在庫数量として、実際に保管されている在庫数量と比較することが可能です。
つまり、棚卸伝票を登録した後に在庫の増減があったとしても、棚卸伝票を登録した時点の在庫数量について棚卸することができます。
逆に帳簿在庫凍結フラグにチェックをしなければ、棚卸中の在庫の増減も含めたSAP上での在庫数量と実際の在庫数量を比較することができます。
実際の在庫数量を入力
実際に保管されている在庫数量を確認し、その在庫数量をT-CODE:MI04にて登録します。
もし上記の在庫数量を変更する場合はT-CODE:MI05を用いて変更することが可能です。
棚卸伝票のすべての明細に対して実際に保管されている在庫数量を入力すると、検数ステータスに”X”が設定されます。(一部の明細に対して在庫数量を入力した場合は検数ステータスは”A”になります。)

在庫差異を転記
在庫の差異を転記することで、SAPの在庫数量を実際に保管されている在庫数量に合わせる決済処理を行うことができます。
決済処理を行う際に、T-CODE:MI20にて在庫数量差異があるかどうかを確認すること可能です。
もし再度棚卸伝票を作成したい場合はT-CODE:MI20のヘッダから「ジャンプ>再検数伝票」(もしくはT-CODE:MI11)を選択し、再度棚卸伝票を作成し棚卸業務をやり直すこともできます。

棚卸伝票のすべての明細に対して決済処理がされると、在庫差異転記 Statusに”X”が設定されます。(一部の明細に対して決済処理をした場合は在庫差異転記 Statusは”A”になります。)

実地棚卸関連のテーブル
実地棚卸で使われているテーブルの関連図は以下で解説しています。ぜひこちらも確認してみて下さいね!
あわせて読みたい
【SAP MM】テーブル関連図(棚卸伝票)
この記事を読むメリット SAPでの棚卸伝票(Physical Inventory Document)関連のテーブルと、そのテーブル関連図について理解できます。 実地棚卸プロセスについての具体…
最後に
実地棚卸業務は在庫を扱う企業にとっては重要な業務になっています。
転記ブロックフラグや帳簿在庫凍結フラグを使うのか・どのようなパターンで棚卸業務をするべきなのかを運用視点でしっかり見極めていきましょう。
SAPを用いた実地棚卸プロセスについての解説は以上じゃ!