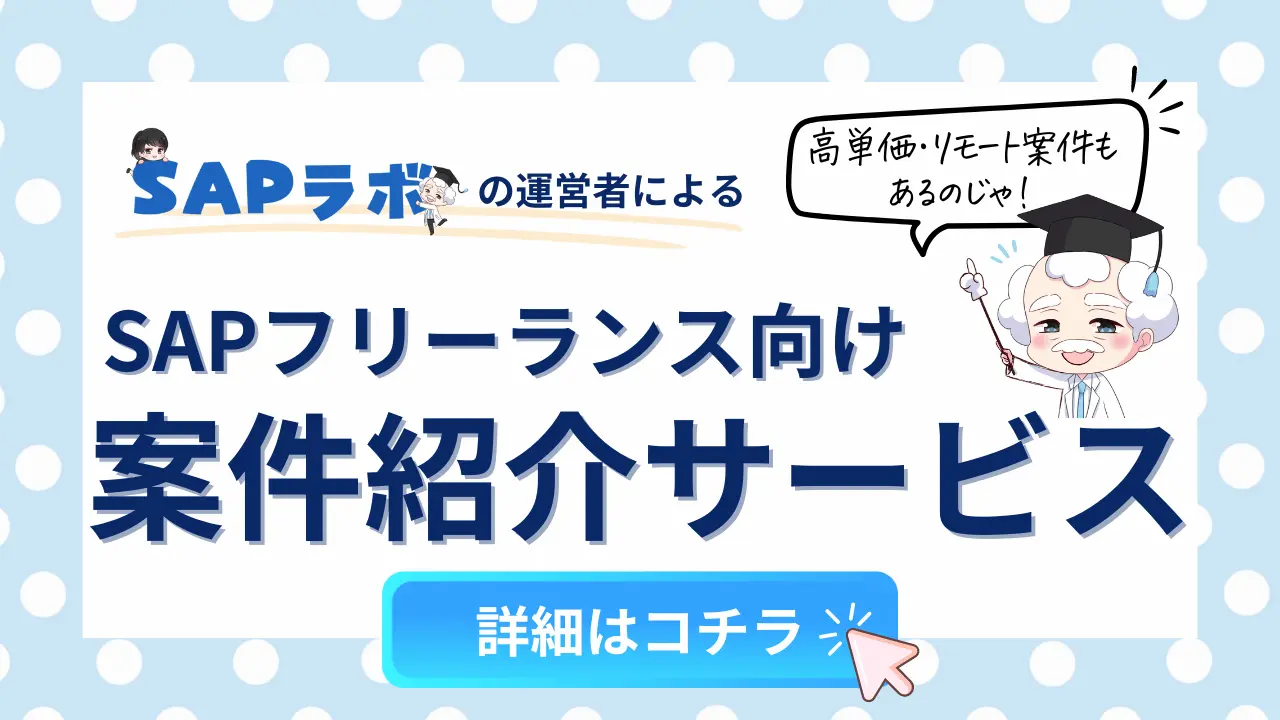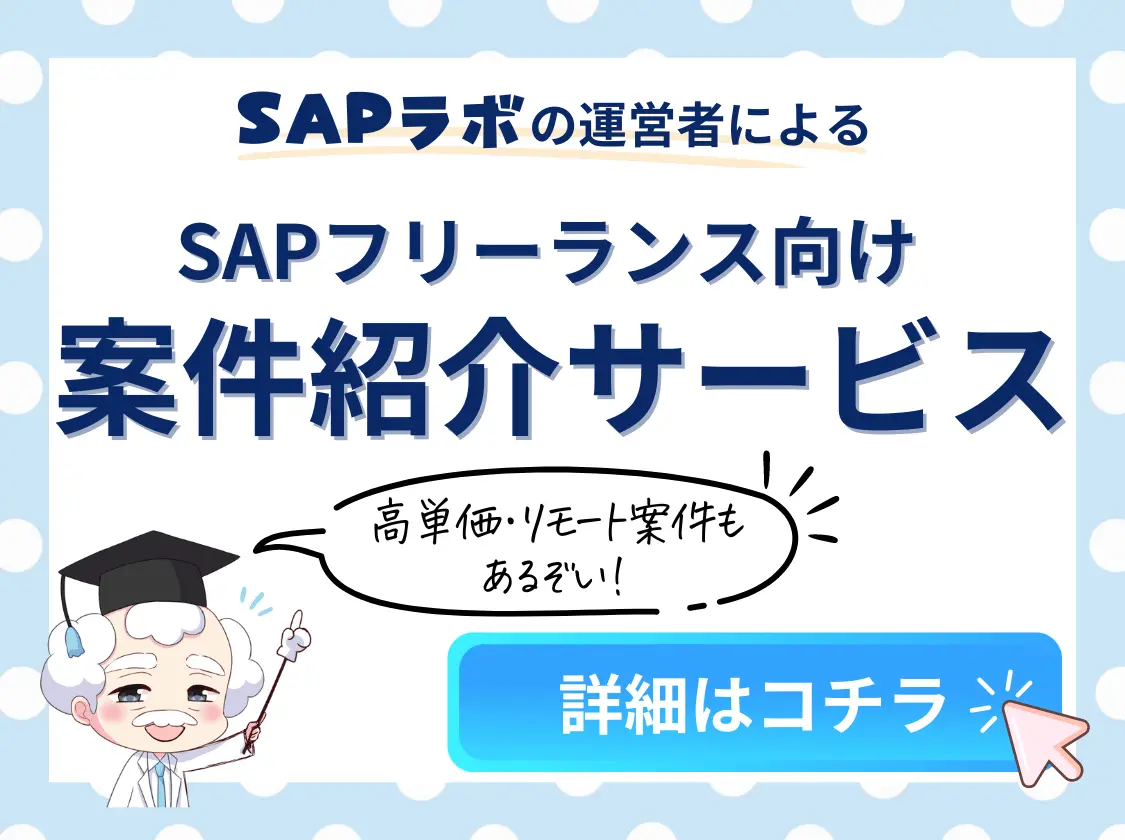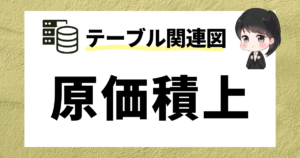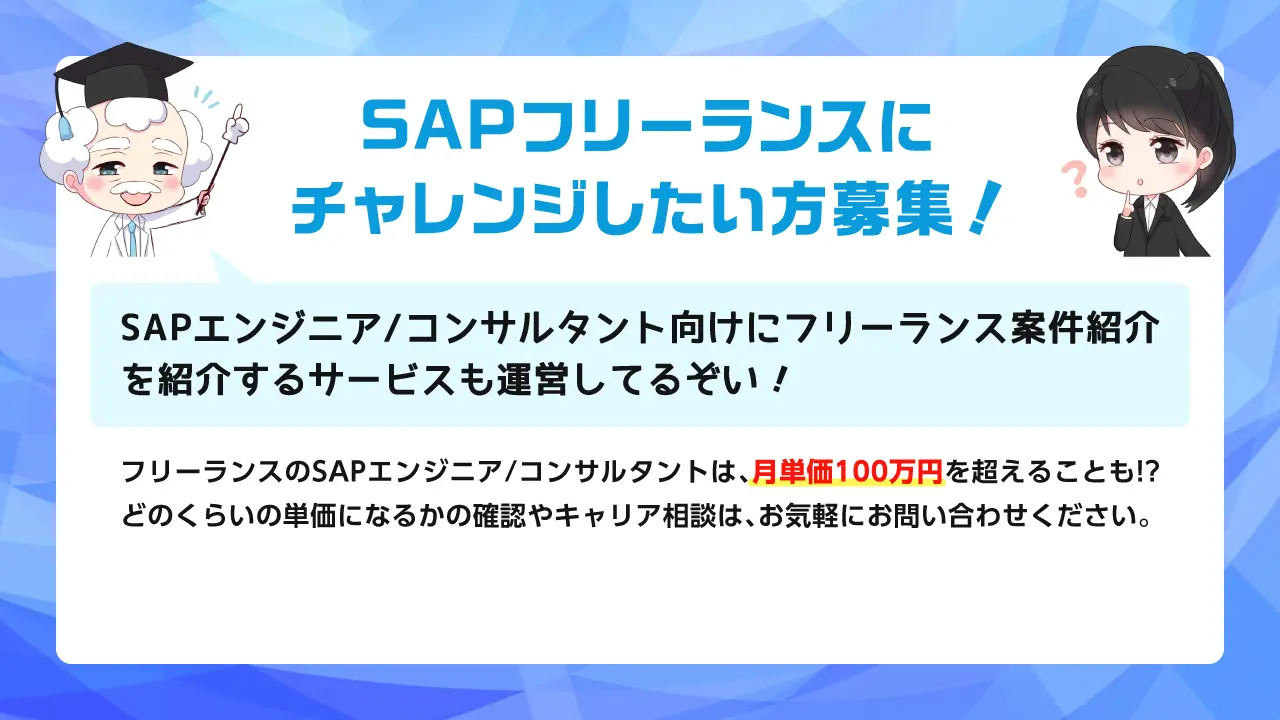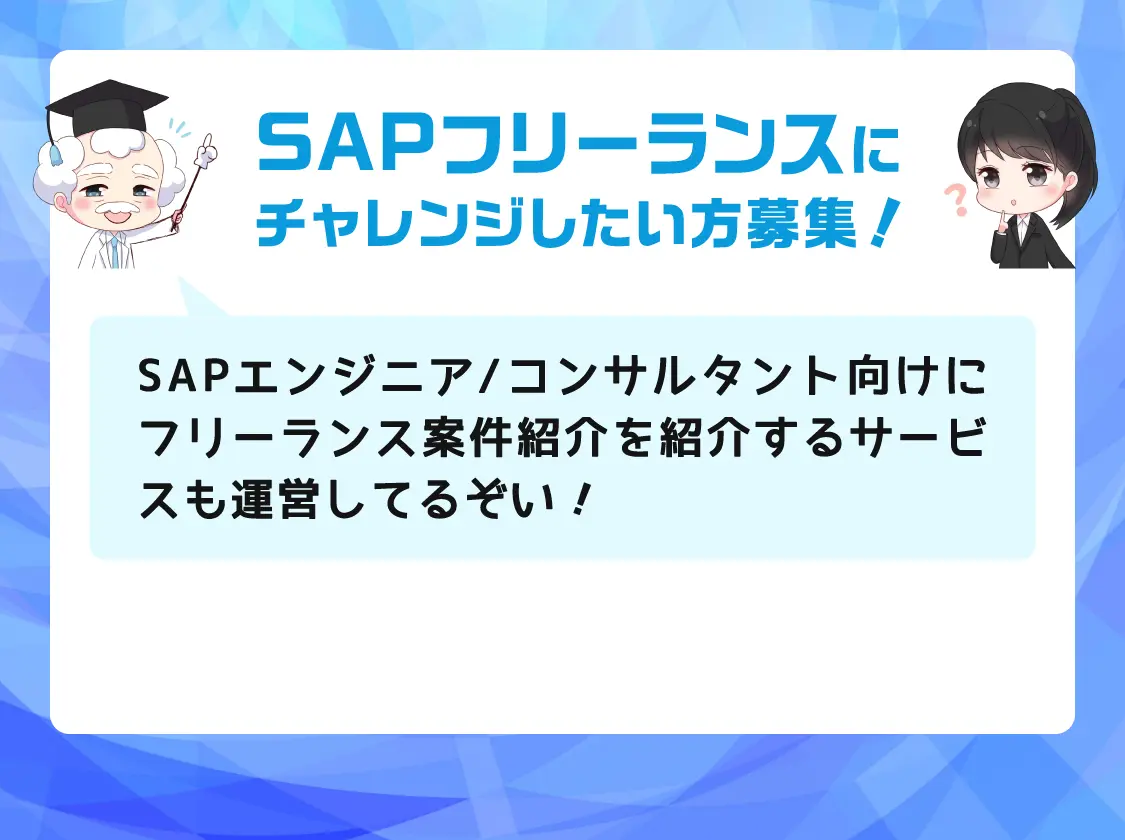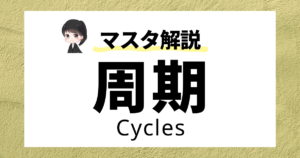この記事を読むメリット
- CK13Nトランザクションを活用した標準原価の内訳分析手法がわかる
- コスト構成(原価要素・活動・部品レベル)を実務でどう読み解くかを理解できる
- 分析視点で必要なSAPテーブルの構造と活用方法を把握できる
製造業における原価管理の中でも、SAPを利用している企業が重視するのが「標準原価の可視化と分析」です。
中でも、T-CODE:CK13Nは、標準原価の詳細な構成を階層形式で確認できる重要な分析ツールです。
CK13Nを使えば、製品に割り当てられた部品・工程・活動・労務費などの内訳を階層構造で表示し、標準原価見積結果に基づく詳細な分析が可能になります。
しかし、「CK13Nは見方がわかりにくい」「原価要素の詳細が追いきれない」と感じている実務担当者も多いのが実情です。
本記事では、標準原価の計算ロジックそのものではなく、その“分析”方法に特化し、CK13Nをどのように読み解き、活用すべきかを実務目線で解説します。
この記事のポイント
CK13Nの概要
T-CODE:CK13Nは、「標準原価見積(Standard Cost Estimate)」の分析・照会用トランザクションコードです。
計算済みの標準原価見積(例:CK11NやCK40Nで作成・保存済)の結果を階層構造で確認できるのが特徴です。
表示される主な情報は次の通りです:
| 表示 | 内容例 |
|---|
| 原価計算構造 | BOM(部品表)や作業手順に基づく階層構造表示 |
| ヘッダ情報 | 原価計算バリアントやBOM/作業手順(レシピ)番号や履歴情報など |
| 詳細一覧(明細) | 直接材料費、間接材料費、活動費、外注費など |
| 原価構成集計 | 原価分類(材料費/加工費/労務費など)の集計表示 |
標準原価見積関連のトランザクションコード
| T-CODE | 内容 |
|---|
| CK11N | 標準原価見積の作成(個別)|シミュレーションも可能 |
| CK24 | 標準原価の本登録(原価を品目マスタに転送) |
| CK13N | 原価構成の照会/分析 |
| CK40N | 標準原価見積の作成(一括) |
標準原価見積に関するトランザクションコード一覧CK13Nの活用方法
原価積上手順
- T-CODE:CK13Nを実行
- 原価見積が登録された品目コードとプラントを入力
- 原価計算バリアントなどの原価計算データを入力
- 階層構造・原価要素・原価構成集計など、表示項目を切り替えて分析
下記の様に、「原価見積」のボタンから詳細の選択パラメータを指定することが可能です。対象の原価見積が参照できない場合は、原価積上ステータスや最終評価日などのパラメータを調整すると参照できることもあります。
 CK13N-選択画面
CK13N-選択画面
分析視点①:階層構造(BOMの分解)
CK13Nの左側に表示される「原価計算構造」には、BOMマスタに基づいた階層構造が表示されます。
表示項目には以下が含まれます:
- 処理ステータス
- 合計金額
- 通貨コード
- 数量
- 数量単位
- その他レイアウトで項目追加可能
階層を展開することで、原価積上を構造的に理解することができ、どの構成品目に原価が集中しているかが明らかになります。
また、構成品目をダブルクリックすることで、その構成品目の原価計算結果を確認することができます。
 CK13N-原価計算構造
CK13N-原価計算構造
分析視点②:ヘッダ
「ヘッダ」では、5つのタブで構成されておりいます。
- 原価計算データ:原価計算バリアント/バージョン/ロットサイズ/ステータスなどの原価計算に関わるデータが表示されています。
- 日付:開始日/終了日や評価日などの原価計算の各基準日が表示されています。
- 数量構成:参照しているBOMや作業手順(レシピ)、製造バージョン、連産品の割当構造などが表示されています。
- 評価:評価通貨や原価計算表、間接費率を制御している間接費キーが表示されてます。
- 履歴:原価計/マーク/リリースの実行者と日付が表示されています。
- 原価:原価ベースや各原価構成ビューごとの総原価/固定費/変動費が表形式で表示されています。
原価タブの原価ベースは、デフォルトでは「原価計算ロットサイズ」に設定されており、品目マスタの”原価計算 1″で定義した値が参照されています。下記の様に「ユーザエントリ」に変更することで、ユーザが自由に原価ベースの数量を変更することができます。
 CK13N-ヘッダ
CK13N-ヘッダ
分析視点③:明細一覧
「明細一覧」では、その品目に紐づいた原価要素(一次/二次)が表示されます。
それらの合計値が、その品目の原価であり、その内訳を確認することができます。
ALVで出力されており、レイアウト変更により項目の表示/非表示や集計、Excelへの出力などが可能です。
明細一覧での主な項目は以下の通りです。
| 主な項目 | 内容 |
|---|
| 明細カテゴリ | 原価発生源に従って自動的に設定されるカテゴリ
(M:品目/E:内部活動/G:間接費/A:連産品など) |
| 資源 | 明細カテゴリに応じて特性が表示される
M → プラント/品目コード
E → 原価センタ/作業区/活動タイプ など |
| 原価要素 | 一次原価要素/二次原価要素 |
| 金額(合計・固定・変動) | BOMや作業手順(レシピ)マスタを参照して表示される |
| 数量 | BOMや作業手順(レシピ)マスタを参照して表示される |
 CK13N-明細一覧
CK13N-明細一覧
前項で説明した通り、表示される金額値や数量はヘッダで選択した「原価ベース」の数量に依存します。
デフォルトでは「原価計算ロットサイズ」に設定されていますので、特に構成品目は上位品目の原価計算ロットサイズを基準にした数量ではなく、構成品目自体の原価計算ロットサイズが表示されていることに注意する必要があります。
例えば、下記の画面の様に、親品目「D-110(SEMI201)」の構成品目「D-120(SEMI301)」は、親品目1PCに対して100PCが消費されます。しかし、構成品目「D-120(SEMI301)」の品目マスタ上(原価計算1タブ)では原価計算ロットサイズが1PCで登録されている為、品目原価見積照会の画面では1PCで金額や数量が計算されます。
そこで、2枚目の画面の様に、原価ベースをユーザエントリにし、数量を100PCと入力すると、親品目で参照した時の数量・金額と整合するようになります。
 CK13N-原価ベースの設定
CK13N-原価ベースの設定
分析視点④:原価構成集計
原価構成集計は、実務上よく使われる集計ビューで、原価構成ごとの集計値を固定費と変動費に分けて確認することができます。ヘッダの原価タブにある「原価構成」のアイコンをクリックすると、明細一覧が表示されていた場所に原価構成集計が表示されます。
この原価構成レイアウトは、カスタマイズ(T-CODE:OKTZ)で定義され、原価構成バリアントに紐づいて呼び出されています。
明細一覧と同様に、レイアウトの変更やExcelへの出力が可能です。
製品別の加工費比率や労務費率、固定費/変動費を分析するには、このタブが最も有効です。
 CK13N-原価構成集計
CK13N-原価構成集計
もっと詳しく💡
コラム:CK13Nは「差異分析」の出発点
CK13Nは、標準原価を構成する要素の可視化だけでなく、後続の差異分析(原価差異分析)や棚卸資産評価にもつながる重要な起点です。
たとえば以下のようなケースで活用されます:
- 製造原価差異(材料費差異/作業時間差異)発生時の要因特定
- 製品別の原価構成比較によるプロセス改善
- 海外工場と国内工場の原価構造比較
関連テーブル
CK13Nで表示される情報は、主に以下のSAPテーブルから取得されます。
| テーブルID | 内容 |
|---|
| KEKO | 原価積上のヘッダ情報が格納されています |
| KEPH | 製造原価の原価構成情報が格納されています |
| CKIS | 明細一覧で表示されているデータが格納されています |
標準原価テーブル
原価積上の詳細な関連テーブルは次の記事が参考になるぞい
あわせて読みたい
【SAP CO】テーブル関連図(原価積上)
【】 以下は原価積上(Costing)関連のテーブル関連図じゃ! 【】 テーブルID テーブル内容KEKO原価積上 – ヘッダデータKEPH原価積上:製造原価の原価構成CKIS…
まとめ
CK13Nは、原価計算の結果を確認するだけでなく、原価構成を多角的に分析するための中核トランザクションです。
標準原価がどのように構成されているかを把握することで、コスト構造の可視化、精度の高い差異分析につながります。また、標準原価はリリースされると最終的に棚卸資産評価へと反映されますので、棚卸資産の信頼性向上につながります。
特に、活動費や間接費が占める割合や部品ごとの原価比率をCK13Nで構造的に分析することで、製造工程や購買戦略などの見直しにも寄与します。
実務では、CK13Nを「確認のためのツール」から「改善のための分析ツール」へと昇華させることが肝要です。本記事がその第一歩となれば幸いです。